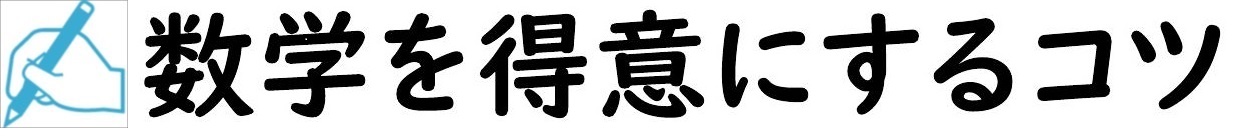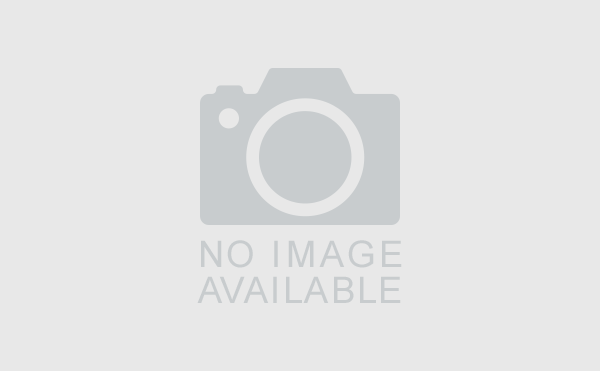問題を解くということ
久しぶりの投稿になります。と言っても,私は「一日一問」解く習慣を持っていまして,ずっと学びはあったわけなのですが,まあ教材研究の一環でもあり,授業のネタにもなっているために,公開はできないでいました。ただ,毎日解いていて,これは知りたいんじゃなかろうか,というか,なぜ解けるのだろうか,という自己分析も,あるいは皆さんの役に立つのではないか,とも思っています。つまりは,ここを見るということは,皆さんの関心は「どうやったら定期テストで点が上がるか」あるいは「どうやったら入試で合格点に達するのか」ということが切実な願いとしてあると思います。そのためには,数学に限ってみても,やはり「問題が自力で解けて,正解する」ということがとても大事で,数学の勉強というのは,結局「問題を解くことだ」と言っても良いと思うのですね。
では,実際,毎日解いている私の実感として,問題を解くとは,だいたい以下の流れになると思いますね。
(1)問題文を見る。
(2)何を問われているか。何かを求めよ,なのか,何かを証明せよ,あるいはその他か。
(3)何が与えられているのか。
(4)これは何の問題なのか。あの問題の類題だな,とか,ああこのタイプか,とか。ああ整数問題か,とか,ああ平面ベクトルか,とか,何らかのパターン認識ができれば,解法が瞬時に思いつくはず…。東大レベルなら,解法A,解法B,解法C…,と思いついた解法をメモ程度で良いので,リストアップしていく。
(5)(4)ができない,つまり題意が取れない時なら,カレンダーにいう「難問対策法」を順次試していくことになる。つまり,具体化してみる,より易しい類題を考えてみる,あるいは知っていることを書き出す…などで「難問を切り崩して」いく。
(6)選んだ解法に従って,計算や処理を進める。
(7)出た答えを検証してみる。例えば,sinx=2とかなら,何かがおかしい。マーク式なら,選択肢にない答えなら,オカシイ。
(8)後は記述式なら,答案用紙かノートに清書していく。
<以下は私の教材研究の話>
(9)反省というか感想戦というか,どんな解法を使ったか,自己分析する。なぜそう思いつけたか,その解説を書き残しておく。
こうした流れを毎日経験しているわけですが,その中で(9)で自己分析した結果,やはり「解法のパーツ」というか,「このシチュエーションでは,だいたいこうするよねえ」というコツがあるわけです。まあ,その解法パターンを「数学のスキーマ」(仮称)として,
まとめておくことも,皆さんの助けになるのではなかろうか,と考えております。おそらくは200パターンぐらいは出るとは思いますが,まあ,現役の教員として隙間時間を使って,書き残しておくのも良いかな,と感じております。
というのも,最近,ブログの統計を見ていると,毎日誰かしら見に来ていただいているようなので,何か書こうかな,と思いました。
まあ,授業の妨げにならない程度に,かつ皆さんの助けになる記事が書ければ良いかな,と今日は思いました。
それではまた。 2025年9月9日
Nasuno Kumao